構造化のリスク ─ 流れを失う仕組みをどう整えるか
構造化という言葉は、
一般的には「情報や議論を整理して、理解しやすくすること」を指す。
複雑なものを分解し、関係を見える形にする。
混乱を減らし、安定を保つための道具だ。
私が言いたい“構造化”は、
「形を留めること」を目的にするのではなく、
「目的のために留めた構造を目的のために流すこと」に焦点を置いている。
構造化は本来、前に進むための補助線のはずなのに、
いつのまにか「整っていること」自体が目的になってしまうことがある。
形は美しくても、流れが止まってしまう。
それが、構造化のリスクだ。
細部を整えるほど、「やっている感」は高まる。
実際、作業は積み上がっていく。
でも、本丸にはいつまでも手が届かないまま、
“整った足踏み”が続いてしまうことがある。
例えば、サイト設計の段階で、画像の大きさや色の濃淡、
位置をピクセル単位で議論してしまうようなものだ。
ある程度かたちが見えてからならその議論は有効だが、
最初からそこに時間を注ぎ込んでしまえば、
いつまで経っても世に出せない。
これは「止まる整い」の典型だ。
細部へのこだわりで流れを留めてしまう。
けれど、この“止まる整い”自体が悪いわけではない。
一度立ち止まり、形を見直すことは大切だ。
問題は、止まったまま流れを通せなくなることだ。
止まり続ければ、整いはやがて滞りに変わる。
生きた整いは止まることと流すことの往復にある。
いったん留めて形を見直し、
そこに再び風を通す。
止まる整いも、流れる整いも、どちらも必要な時間だ。
大事なことは、止まったままにしないこと。
留めたものに再び流れを通せば、
構造はまた動き出す。
完璧を目指す人ほど、この構造化の罠に陥りやすい。
形を整えることに全力を注ぐあまり、
その中を動かす流れを失ってしまう。
整えるとは、止まることと流すことが交互に働く設計のこと。
不完全でも、動きを保つ仕組みを持てば、全体は整う。
構造を描く手は常に問い続けたい。
「これは、動くための構造か?」
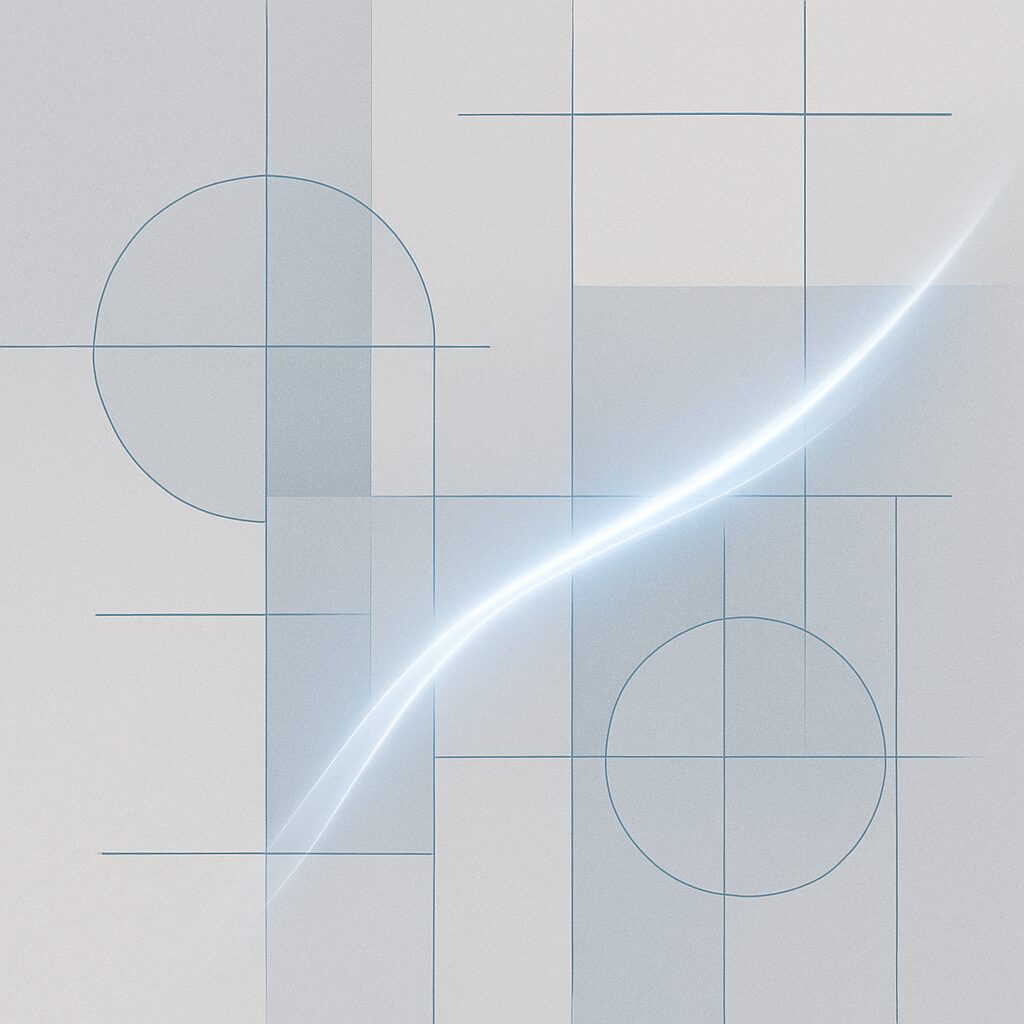


コメント