仕組みを整えるということ
仕組みが曖昧なまま運用されると、
意図せずして“隙間を抜けてしまう”ことがある。
誰かが怠けたわけではなく、
ただ、構造が整っていなかったために、
意図と結果のあいだにずれが生じてしまう。
そうして生まれたずれは、やがて溝になる。
評価する側とされる側の軸が合わなくなり、
努力の方向と評価の基準が噛み合わなくなる。
お互いが誠実に向き合っていても、
測る物差しが異なるだけで、誠実さは伝わりにくくなる。
その不一致が積み重なると、
信頼関係で満たされた空間は、静かに揺れ始める。
仕組みを整えるとは、
この“軸のずれ”を最小限に抑えるためのことだ。
個人の感覚ではなく、共有できる基準で対話できるようにすること。
正しさや誠実さが、共通の文脈の中で認識されるようにすること。
「仕組みを整える」という発想は、安藤広大氏の著書『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)にも通じる。
現場で起きる課題を“人の問題”ではなく“構造の設計”として捉える視点。
自分の立場やチームの関係を整えるうえで、一度は読んでおきたい一冊だ。
整えるとは、溝をなくすことではない。
むしろ、溝が生まれたときに
それを構造として説明できる状態をつくること。
責めるためでなく、理解し合うための仕組み。
それが整っているということだ。
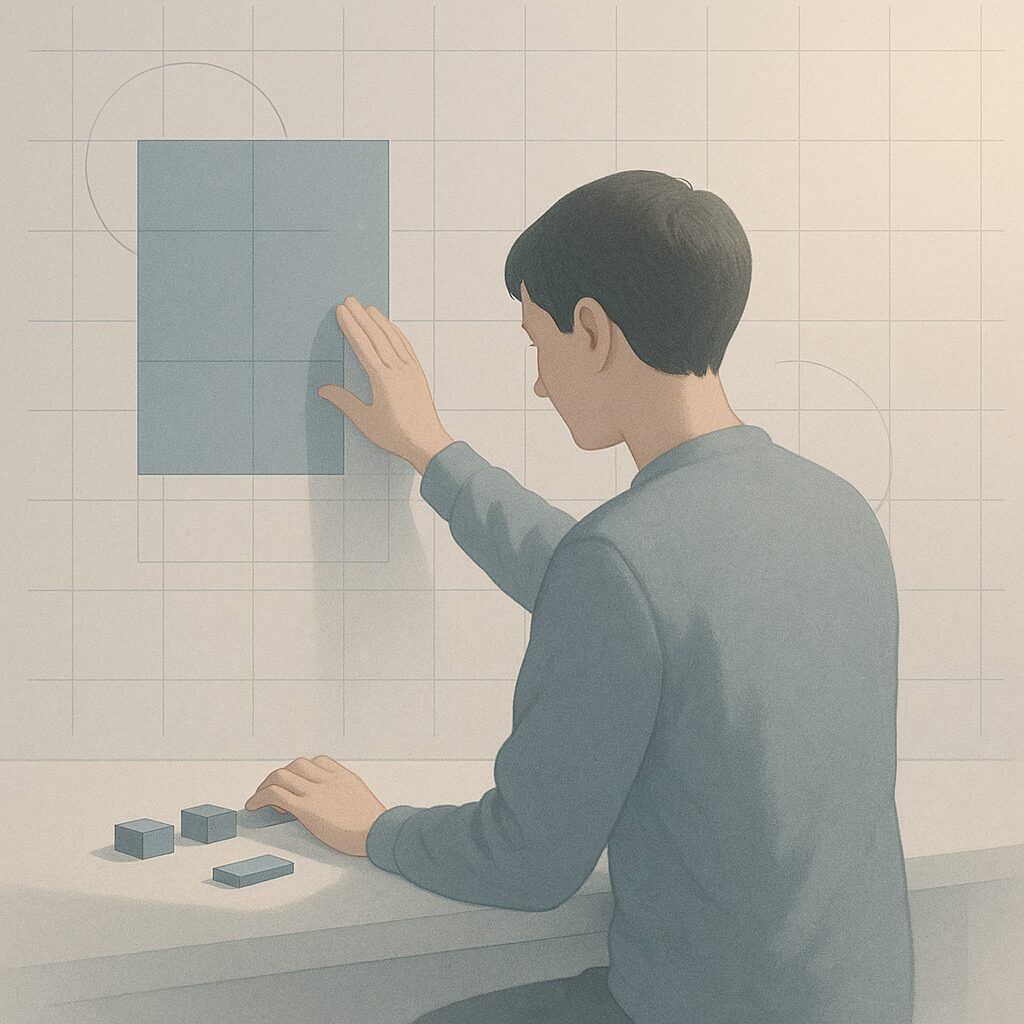


コメント