―― 思い出す努力がつくる、静かな定着
学びは“取り出す”ことで整う
―― 思い出す努力がつくる、静かな定着
学びを整える方法は、覚えることではなく、取り出すことにある。
ノートを何度も読み返すよりも、
「あれ、何だったっけ?」と自分の頭の中に手を伸ばす。
その一瞬の“思い出す努力”が、記憶を深く根づかせてくれる。
この「取り出す学び」は、心理学では 想起練習(retrieval practice) と呼ばれている。
人は、思い出そうとする行為そのものによって、
記憶のネットワークを再構築しているらしい。
完璧に思い出せなくても構わない。
むしろ、曖昧なまま取り出して、確かめ直すことが大切だ。
それを繰り返すうちに、知識は“使える形”に整っていく。
学びとは、詰め込むことではなく、呼吸のような往復運動だ。
吸い込んで、取り出して、また吸い込む。
その静かなリズムが、学びを生かす。
心理学者の ヘンリー・ローディガー らの研究では、
単に復習するよりも「思い出す練習」をしたグループの方が、
1週間後の定着率が約2倍高かったという。
つまり、“取り出す”という行為は、
脳の中で情報の通路を磨き直すようなもの。
学びを整えるとは、記憶を再び“流れる状態”に戻すことなのだ。
この考え方をより深く理解するのにおすすめなのが、
『科学的根拠に基づく最高の勉強法』(安川康介/KADOKAWA, 2024年2月15日)。
認知心理学や神経科学の知見をもとに、
「思い出す」「間を空ける」「眠る」といったシンプルな行動が
学びの効率ではなく**“質”を整える**ことをわかりやすく解説してくれている。
忘れて、思い出して、確かめ直す。
その小さな循環のなかに、
ほんとうの「整える学び」がある。
取り出すたびに、脳の中が少しずつ静かに整っていく。
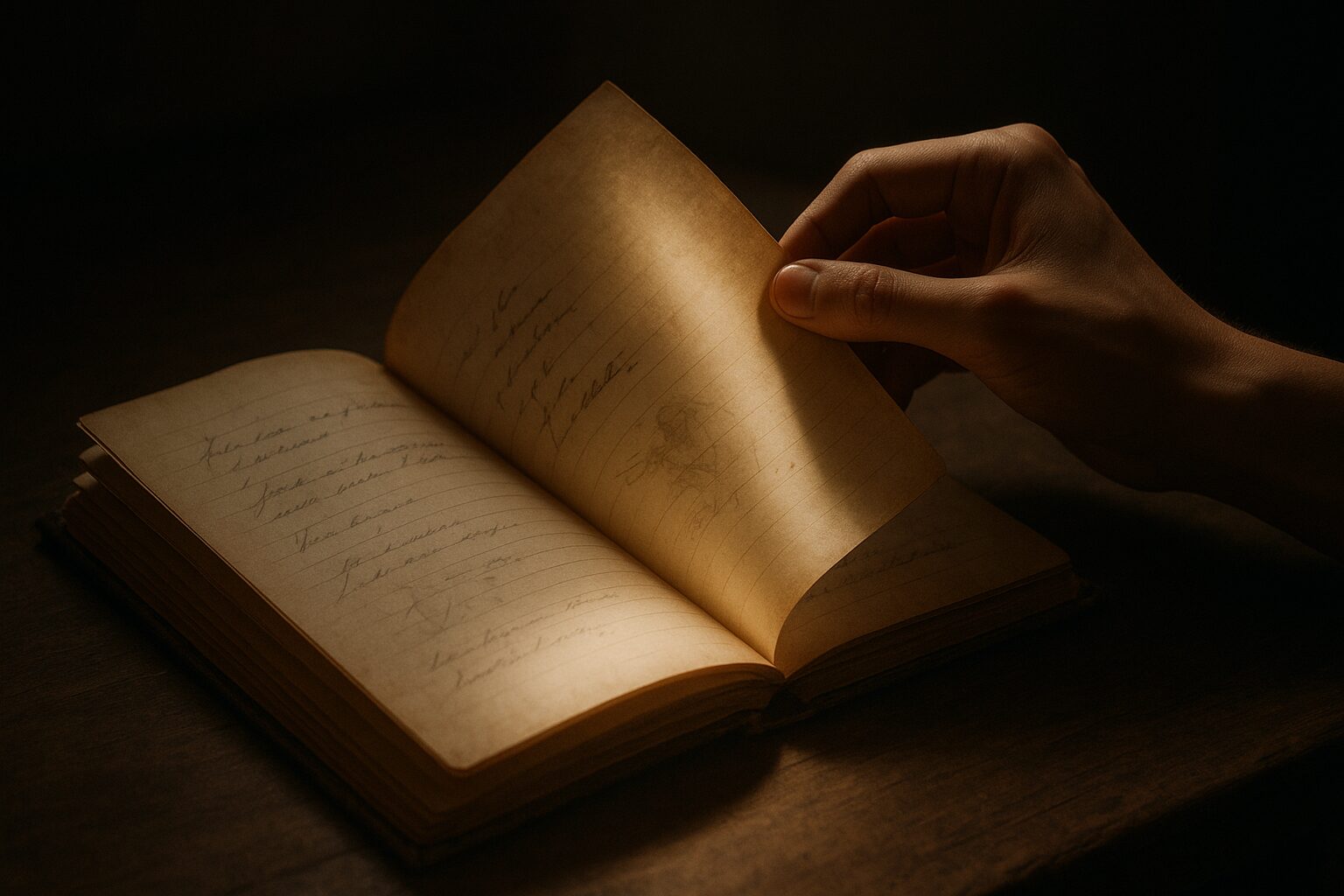


コメント